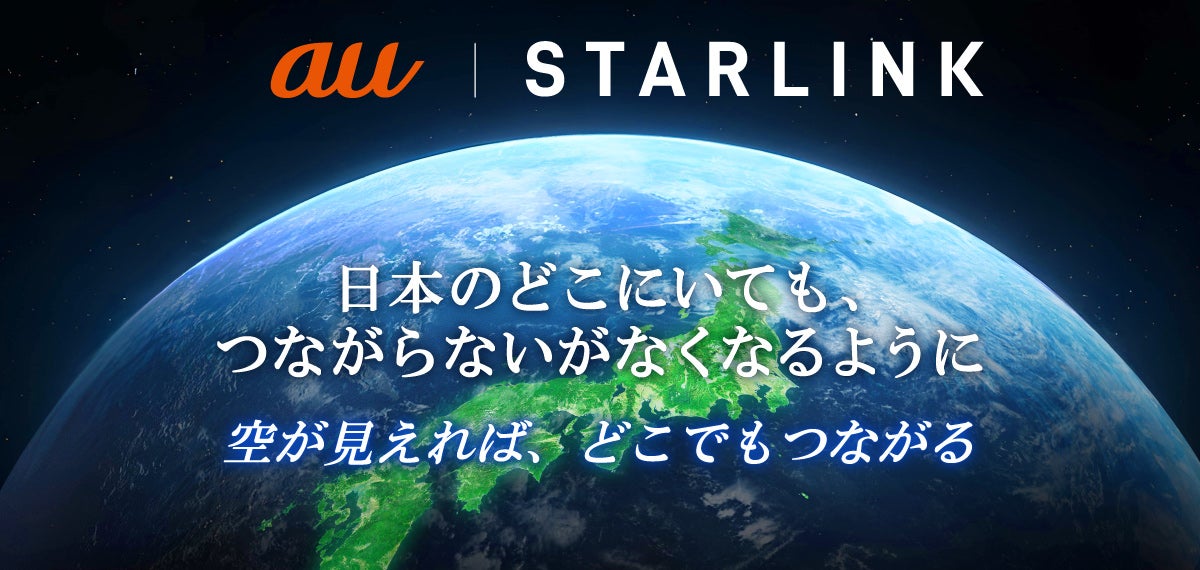「生物多様性」というキーワードが、環境課題のテーマとして改めて注目を集めています。
そのきっかけとなったのは、2022年12月に開催された生物多様性条約締約国会議(COP15)*¹で、2030年までのネイチャーポジティブ(生物多様性の損失を止め、回復に反転させること)に向けた世界目標が採択されたことです。
*1 生物多様性条約締約国会議(COP15):生物多様性条約(Convention on Biological Diversity:CBD)の締約国による会議のこと
私たちの生活は、地球上の生態系に支えられています。持続可能な社会を実現するために、KDDIは「ネイチャーポジティブ」に貢献することを目指し、以下の取り組みを進めています
取り組み1:国内通信事業者で初めて*²「TNFDレポート」を開示
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が公開した、自然関連のリスクと機会が企業の財務に与える影響を開示する枠組みを示したTNFDβv0.4を参照し、生物多様性を含む自然資本に関してKDDI事業が有するリスクと機会を分析し、その結果を2023年6月9日に開示しました。
また、2023年9月にTNFD最終提言v1.0が公開されたことを受け、KDDI TNFDレポート 2023 v1を2023年12月4日に公開しました。
*2 2023年6月9日時点、KDDI調べによる。
取り組み2:自社通信事業における生物多様性へのリスクを最小化
通信設備設置における土地利用変化や陸域生態系への影響リスクを抑えるため、土地の生態系に配慮した工事を行っています。
たとえば、陸域では水力発電を活用した基地局の設置や、景観に配慮した施工で環境への影響を最小化しています。海域では、サンゴを避けた海底ケーブルのルート設計や、ウミガメの産卵期を避けた施工計画などを実施しています。
(1).jpg)
取り組み3:パートナーとともに生物多様性保全への貢献機会の創出
バイオーム社の有する生物調査の知見と、KDDIのデジタルテクノロジーを組み合わせ、生物情報を可視化する取り組みを行っています。
2023年9月、沖縄県西表島の生物多様性保全を目的に、スマホアプリ「Biome(バイオーム)」と「Starlink Business」を活用した外来種調査を実施しました
(1).jpg)
生物多様性を守るために。KDDIは、「ネイチャーポジティブ」に向けた取り組みを推進していきます。
他社に先駆けたTNFDレポート公開にこだわった理由
地球上の生物種の7割近くが、過去50年で失われてしまいました。
2022年12月に開催された生物多様性条約締約国会議(COP15)で、生物多様性の保全に関する世界目標が合意されたことを受けて、KDDIも生物多様性保全に対する取り組みを強化しています。
COP15と並行して、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)という、自然関連のリスクと機会が企業の財務に与える影響を開示するための枠組みの整備が進んでいます。
KDDIでもこの枠組みを利用し、2023年6月に国内の通信事業者として初めて、TNFDレポートを公開しました。
「いち早く行動することで、私たちの思いに共感し、生物多様性の保全という課題に共に取り組んでくれるパートナーを見つけることも、レポートを公開する目的のひとつでした」(KDDI サステナビリティ企画部 大藤桃子)
(1).jpg)
TNFDレポートでは、私たちの主力事業である通信事業に焦点を当ててリスクと機会を分析しました。その結果、現時点で大きなリスクをもたらす行動は取っていないことが確認できました。一方、機会の分析は部門横断でのワークショップを通じて行いました。その結果、KDDIが持つテクノロジーが新たな事業機会を生み出す可能性があることが見えてきました。
通信エリア外での外来種調査
これまでKDDIは、社会貢献活動として小学生向けの環境教育や全国各地での森林保全活動など、生物多様性の保全に取り組んできました。しかし、社会全体を巻き込んで持続可能な活動を進めるためには、ボランティア活動だけでなく、ビジネスとして利益を生み出すことも必要だと、サステナビリティ企画部の柏木真由子は指摘しています。
(1).jpg)
生物多様性の保全とビジネスを結びつけるひとつの取り組みとして、2023年9月に、株式会社バイオーム、沖縄セルラー電話株式会社と共に、西表島で外来種調査を行いました。
(1).jpg)
「以前から、通信技術が生物多様性の保全に大きく貢献できる可能性があると考えていたものの、具体的に何をすべきか、明らかではありませんでした。そんな中、生物情報の可視化に取り組むバイオーム社と出会いました。バイオーム社は、誰もが生物情報を収集できる『Biome』というスマートフォンアプリを提供しています」(柏木)
「バイオーム社とどのような取り組みができるか議論していた時、国立公園や山奥などの生態系が豊かなエリアでは携帯電話の電波が不安定であるため、アプリを使った調査が難しいという課題が明らかになりました。そこで、衛星通信とバイオーム社の調査ノウハウを組み合わせれば良いのではないかと考え、Starlinkを活用した生物調査を発案し、西表島の通信圏外エリアで外来種調査を実施するに至りました」(柏木)
(1).jpg)
(1).jpg)
西表島での調査で得た知見を活用し、今後は企業や自治体への提案に力を注ぎたいと柏木は意気込んでいます。
「さまざまな自治体に話を伺うと、地域ごとに課題が大きく異なることがわかります。例えば、住民への環境教育の必要性や、希少種保護のための外来種調査など。それらの課題に対して、KDDIのアセットを活かした解決策を考えることで、単なる社会貢献だけではなく、ビジネスとしても成り立つ持続可能な活動の仕組みを作りたいと考えています」(柏木)
.jpg)
地道な改善と持続可能な活動の仕組みづくりを続けていく
「多くの企業や自治体が、変革の必要性を感じつつも、生物多様性という幅広いテーマに対してどこから手をつければ良いか迷っています。KDDIも、このテーマを単独で解決するのは難しく、様々なステークホルダーと共に取り組むことの重要性を認識しています」(大藤)
.jpg)
KDDIでは、TNFDレポートなどをきっかけに共感していただけるパートナーと協力しながら、生物多様性により一層配慮した事業に変革していく取り組みを進めています。
そのためには自社の情報開示が重要であると認識し、TNFDレポートのアップデートにも力を入れています。2023年8月からは、KDDIの通信事業にかかわる日本国内の基地局、データセンター、そのほかの拠点のうち、保護区など特に重要なエリア周辺に建設されている拠点について、周辺の環境を分析し、植物の外来種・希少種の分布を推定・評価することで、優先的に対応を検討すべき拠点を特定しました 。
「今回の分析結果を基に、生物多様性保全への貢献を実現するために策定した生物多様性行動指針に基づき、土地の特性に応じた対応をさらに検討する予定です。一つひとつの影響は小さいかもしれませんが、確実に取り組んでいきたいと考えています」(大藤)
「生物多様性から人々が受ける恩恵は、物質的なものだけでなく、自然とのふれあいによる心の充足や土地への愛着など、精神的・文化的なものも含まれます。私たちのつなぐチカラとパートナーの技術を組み合わせて、豊かな自然環境を保護し、自然を身近に感じる活動に貢献していきたいです」(柏木)
これからもKDDIは、豊かな地球環境を次世代につなぐため、持続可能な生物多様性保全に力を注いでいきます。
自然資本に配慮した事業計画の重要性
多くの企業は、事業運営における資源の利用や環境汚染など、生物多様性や自然資本と密接に関わっています。
KDDIの通信事業も例外ではありません。例えば、通信設備の設置では土地利用変化や陸域生態系への影響が懸念されますが、自治体や政府と協議しながら、その影響を最小限に抑えための工夫を行っています。 具体的には、海底ケーブルの敷設においては、サンゴを避けるルート設計やウミガメの産卵期を避ける施工計画を検討しています。陸域の基地局敷設においては、基地局の電源供給に水力発電を導入するなど、地域の生態系に配慮した工事を行っています。
諦めない交渉の末に確保した環境にやさしい電力供給源
日本初の世界遺産に登録された屋久島。その中でも人気の観光スポットである白谷雲水峡の登山道において、KDDIは2022年10月、他社に先駆けて通信エリア化を実現しました。
この取り組みでも、自然環境に配慮した施工が行われています。
現場施工を担当したKDDIエンジニアリング 松村京孝と行實丈夫に当時の話を聞きました。
.jpg)
「白谷雲水峡の基地局敷設において、環境に配慮した工夫は3つあります。それは、水力発電による電力供給源の確保、衛星通信を活用したバックホール回線、そして景観に配慮した施工です。」(松村)
この基地局への電力供給は、自治体が所有する既存の水力発電設備から行っています。通常、電力会社による供給がないエリアでは新たな工事が必要ですが、今回の場合、約10㎞の電線を新設するために、多くの木を伐採する必要がありました。
エリア化の検討を開始したのは2014年。登山道の入り口に町が設置した水力発電があったため、まずそれを利用できないかと町へ交渉を試みました。
しかし、公益性の点から一社だけに電力を供給することに関するハードルが立ちはだかり交渉は難航。自前で水力発電をすることも検討しましたが、水利権の問題などで実現は難しい状況でした。
.jpg)
約6年後。多くの人が訪れる場所で通信が届かない状況を放置するわけにはいかないと考え、再度交渉に臨みました。結果、町の水力発電から電力を得られることとなりました。
「最終的には、私たちの思いに共感いただき、電力を使わせていただくことができました。あきらめずに交渉を続けて、本当に良かったです」(行實)
.jpg)
バックホール回線の構築についても、通常は光ファイバーを基地局まで引くのですが、電力供給と同様に大規模な工事が避けられず、環境への影響が懸念されました。
そのため、auがカバーしている島内のエリアの電波を拾い、レピータ*1を使って増幅するなどの方法も試しましたが、鹿児島本土や種子島などの基地局が発している電波と干渉してしまい、難航しました。
そこで地上からのアプローチをあきらめ、衛星通信を活用して空から接続することに挑戦しました。これにより、新たな建造物を建てず、環境への影響を最小限に抑えた通信エリアの拡大を実現したのです。
*1 レピータ:電気信号をより高いレベルや出力・再送信する装置
「通信がつながらないと、緊急時に連絡を取ることができないなど、命の危険にもつながります。そのため、日本のどこでも快適な通信環境を構築することは非常に重要です。しかし、人間の都合で自然環境を破壊してはいけません。
これからも、快適な通信環境と自然環境保護の両立を目指し、再生可能エネルギーの活用など自然環境に寄り添った技術進化を推進していきたいです」(行實)
生物界のGoogleをめざして
生物の保全活動や研究は、どこにどんな生物が、どのくらい存在しているのかという分布データ(生物情報)が欠かせません。
「我々は、この生物情報を収集し、データプラットフォームを構築することを目指しています」と、株式会社バイオーム 取締役 COO 多賀洋輝さんは言います。
(1).jpg)
バイオーム社が開発したアプリ「Biome」は、「いつ、どこに、どんな生き物がいたのか」という生物の分布データを集めることを目的としています。
「目指すところは、『生物界のGoogle』です。Googleは世界中の検索ワードをデータプラットフォーム化しています。私たちは生物業界で同様のことを目指しているのです」
現在、バイオーム社のデータは、自治体との生物保全活動や研究をはじめ企業のCSR活動やTNFDの取り組みの基礎データとしても活用されています。さらに、エコツアーや都市設計など、会社を立ち上げる前には想像もしていなかったビジネスの可能性も見えてきたと、多賀さんは語ります。
(1).jpg)
特に印象的な活用例として、「リジェネラティブツーリズム」という新しい観光の形があります。これは、観光客が増えるほど自然が回復するという考え方で、北海道の上川町では、登山客が「Biome」を使って生物情報を投稿し、それを保全研究に役立てています。観光客の行動によって自然が保全され、その豊かな自然を目的に観光客が訪れるというポジティブなフィードバックループが生まれているのです。
完全独自開発のAIを搭載した「Biome」
アプリ「Biome」は、山登りのようなアウトドア活動として生き物探しを楽しんでもらうことを目指しています。
名前判定機能、SNS機能、コレクション機能、図鑑機能を備えており、生き物探しを総合的にサポートします。
(1).jpg)
生物調査を行うための最初の障壁は、その名前がわからないことです。
そこでバイオーム社は、生物の名前を判定するAIを開発しました。現在では、日本国内で見られる動植物のほぼ全種に外来種や一部の園芸品種も加えた、約10万種の動植物に対応しています。
このAIはバイオーム社の独自開発であり、他の情報提供アプリとは異なる特性を持っています。
例えば通常の情報提供アプリは、ある蝶の画像を判定すると、全世界の蝶のリストから検索を行う仕組みになっています。
しかし、生物は地域により異なるため、専門家が判定を行うときには、まず「夏に西表島で見られる蝶」のように具体的な条件で絞り込みを行います。
このアプローチをヒントに、データの位置情報や時間情報から、その時期・場所にいる生物リストを作成し、画像判定を行います。これにより、AIの精度が大幅に向上しました。
さらに、毎日大量に寄せられるユーザーからのデータにより、日々精度が向上しています。
西表島での外来種調査の目的
2023年9月、バイオーム、沖縄セルラー電話、KDDIは沖縄県西表島の電波の不安定なエリアで、Starlinkを活用した外来種調査を行いました。
(1).jpg)
生物調査は現場でのメモ取りや写真撮影後のデータ整理が非常に大変ですが、「Biome」を使えば現場でデータ収集をしながら整理ができます。
しかし、自然豊かな場所では通信が不安定なことが多く、「Biome」でのデータ収集が難しいことが課題でした。この課題を解決するために、コンパクトで持ち運び可能なStarlinkが活躍しました。
(1).jpg)

本取り組みにおけるバイオーム社の目標の一つは、集めたデータを生物保全に活用することです。特に外来種防除を重要課題として設定していました。島の生態系は外来種に対して非常に脆弱で、新たな強い生物が入ってくると、元々の生態系が立ち直ることが難しくなります。早期の発見と対応が重要ですが、観光客が「Biome」を使ってデータを提供してくれるようになれば、理想的な監視システムが実現できると考えています。
KDDIとの共創の意味―生物情報の収集に不可欠な情報インフラ
自然資本や生物多様性に関するプロジェクトは、そのスケールが非常に大きいため、情報通信、運輸業、プラント業など、広範囲の社会インフラを持つ企業とのパートナーシップが重要だと、多賀さんは考えていました。
「KDDIさんから声掛けをいただいた時には、『(待ち望んでいた機会が)来た!』という感じでした。KDDIさんはさまざまな研究開発を行っているので、Starlinkだけでなく海中のデータ収集方法など、他の領域でも一緒に取り組むことができるのではないかと期待しています」
生物多様性の普及と主流化をめざして
バイオーム社は、2つの大きなミッションを掲げています。1つ目は、生物多様性に関するプラットフォームを国内外に展開すること。そして、2つ目は、生物多様性の主流化です。
脱炭素などと比べて、生物多様性に関する認識は一般生活者の間で遅れています。行政や企業の動きは生活者の意識に大きく影響されるため、生活者に生物多様性に対する意識を持っていただくことが重要で、普及啓発活動を進める必要があると、多賀さんは語ります。

「『生物多様性とは何か』を理解できる人を増やすことが目標です。脱炭素と比べて生物多様性は複雑な領域ですが、既存のユーザーインターフェースをもつ我々こそが、分かりやすく伝えていかなければならないと考えています」